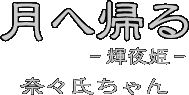「・・・司さん?」
部屋の中から、遠慮がちなか細い声が聞こえた。
振り返ると、厚手の遮光カーテンの陰から顔を覗かせる沙希・・・婚約者が目に入る。
「どうかしました?こんな寒い日に、そんな格好で外へ出て・・・」
心配そうな表情で、厚手のガウンを持って俺の横へと並ぶ。
肩にかけようとしたその手を制し、いらない・・・と首を振ると、沙希の顔に不安が広がった。
「長風呂しすぎて、のぼせたから・・・」

彼女から目を反らし、再び空へと向ける。
細い細い月の光は、あまりにも儚すぎて、俺には届かない。
それでもこうして見つめていれば、この想いが少しでもあいつに届くような気がした。
「・・・そろそろお部屋に戻りませんか?風邪ひいてしまいますよ」
「・・・ああ」
そう答えるものの、目は空から離せない。
不思議そうに、隣に立つ彼女も空に視線を走らせた。
「・・・何か、見えますの?」
「・・・かぐや姫」
一瞬目を丸くして驚き、そのあと、口に手を添えて控えめに笑った。
司さん、冗談がお好きですね・・・
そんなつもりはなかったけれど、大抵の人間はそう捕らえるだろう。
俺も、笑って見せる。
・・・笑顔を作るのは好きじゃない。
けれど、慣れてしまった。
感情のない、それでいて人を安心させる笑顔を作る事に・・・
「・・・明日も早いから、もう寝る」
身体も冷え切ってしまい、そろそろ限界だ。
これ以上ここにいたら、本当に風邪を引いてしまう。
部屋に足を一歩踏み入れた瞬間、心地よい暖かさが身に染みた。
沙希が部屋に入ると、大きくて頑丈な窓を閉める。
外気が遮断され、彼女の光は、もう見えない。
「司さん、今日は・・・」
「俺はゲストルームで寝るから、寝室は自由に使って」
彼女の言葉を遮り、部屋を出た。
『今日は一緒に寝てもいいですか?』
彼女が言いたかった言葉くらい、容易に想像できる。
この屋敷に来てから毎日、その言葉を俺に伝えようと必死なのだから。
でも、そんなこと出来るはずがない。
他の女を・・・抱けるはずがない。
ゲストルームの窓を空け、再び、空を見上げた。
月は雲に隠れ、その姿は見えない。
「・・・お前、俺の事ちゃんと見てる?」
胸元で淋しく揺れるリングをぎゅっと握る。
ひんやりとした小さなそれは、手の熱ですぐに暖かくなったが、俺の心は冷たいままだ。
沙希は、俺の『笑顔』が好きだと言った。
瞳が優しいからだ・・・と。
優しい?そんな事あるはずがない。
ただ、諦めてるだけだ
自分の未来に、夢に、全てに
色を失った瞳が、彼女をそう錯覚させているだけ
「・・・なあ、俺の事覚えてるか?すこしは、俺の事考えてるか?」
あの日、あいつが残していったリング。
『いつか来る日のために』と、俺が贈ったもの。
どうして残してったんだ?
もう、二度と会わないってこと?
それとも、これをお前に渡すチャンスを、もう一度だけくれるってこと・・・?
「・・・俺も、月に連れてけよ。・・・迎えに・・・来いよ・・・」
叶うはずのない独り言だとわかっている。
それでも、呟かずにはいられなかった。
窓を閉め、ベッドにもぐる。
目を閉じると、脳裏に浮かぶあいつの姿。
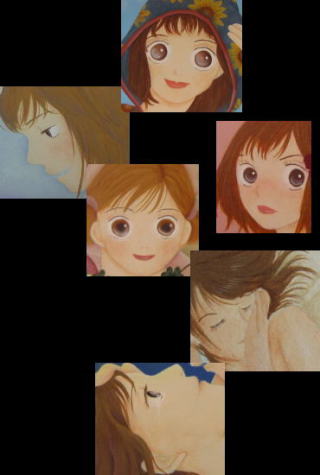
泣いたり
笑ったり
怒ったり・・・
どんな表情も、かけがえのない宝物だ。
強い意志のこもった大きな瞳
好奇心旺盛な、キョロキョロとよく動く瞳
少し低くて丸い鼻も、小さな口も
小さな手も、すぐに赤くなる頬も
ベッドの中での、妖艶な泣き顔も
全てを思い出しながら、熱く膨張した自分自身に手を添えた。
あいつの全てを感じながら、そっと目を閉じる。

『つくし・・・』
最後の時を迎える瞬間、俺はそう呟くだろう。
月へ帰った『かぐや姫』の名前を・・・・・